|
|
![[そばゆ]](img/sobayu2.gif)
![[タイトル画像]](img/title.jpg)
![[そばゆ]](img/sobayu1.gif)
| |
| ◆塩の紹介◆ | ||
|---|---|---|
| ●塩の効能 「塩分を摂りすぎると、高血圧になる」と常識のようにいわれていますが、これに異論を唱える学者や有識者はたくさんいます。一方で、塩が体に不可欠なものであるということに反対する人はいません。体に必要なナトリウムは、人間の体内では生み出すことができないのです。ですから、外から摂取する必要が生じてきます。もし、塩分を必要量摂らなかったら、人の体はどうなるのでしょう?一般的には、新陳代謝の衰えや消化能力の衰え、筋肉、腎臓などの働きが低下するといわれています。 ●塩の製法 【 海水 】 雨が少なく乾燥した地域では、海水を塩田に引き込み、太陽熱と風で水分を蒸発させ塩の結晶を得る天日製塩の方法がとられています。 日本では、多雨多湿の気候から天日製塩は難しく、古来から海水を一旦濃縮し、それを煮つめるという2段階方式で塩をつくってきました。 この海水を濃縮する方法が、塩浜(揚浜式塩田、入浜式塩田、流下式塩田)やイオン交換膜法であり、最近はタワー式やネット式などいろいろな方法で行っている商品も見受けられます。 【 岩塩 】 大昔、海の一部が大陸の移動や地殻変動で陸地に閉じ込められ海水の湖となったものが干上がって塩分が結晶化し、その上に土砂が堆積してできたと考えられています。 形成時期は5億年から200万年前といわれ、世界にある岩塩の推定埋蔵量は、現在知られているだけでも数千億トンにもなり、岩塩由来の地下かん水も含めると、世界の塩の生産量の約3分の2が岩塩からつくられています。 このように地球上には多くの岩塩が埋蔵されていますが、日本国内には存在しません。 岩塩の採鉱法には「乾式採鉱法」と「溶解採鉱法」の2通りあります。 岩塩は重金属などの異物を含んでいることがあるため、食用にはそのまま供されることは少なく、一旦水に溶かして異物を取り除いてから再び結晶化させる方法がとられています。 【 地下かん水 】 地下水が岩塩層を溶かし、濃い塩水になったものがほとんどで、一部は地表から噴出しているものもあり、塩泉と呼ばれています。 地下かん水は岩塩層の近くにあるので、岩塩を産出する地域に見ることができます。 【 塩湖 】 大昔、海だったところが地殻の変動で陸に封じこめられ、水分が蒸発して濃度が濃くなったのが塩湖(濃い塩水の湖)です。 乾燥した地域に多く、天日製塩と同じ方法で塩がつくられますが、季節によって自然に塩が結晶する塩湖もあります。 【 藻塩 】 見た目の特徴は、薄い茶色であること。ホンダワラの成分の影響で、この色になります。海藻を利用するため、海藻が多く持つ成分であるヨード分が豊富なのも特徴のひとつ。海水を濃縮した天然塩であるため、カルシウム、カリウム、マグネシウムなど、海水に溶け込んだミネラル分を多く含んでいます。 また、塩分(塩化ナトリウム)そのものの濃度は低いため、塩でありながら塩分控えめであるともいえます。味も純度の高い塩に比べ、まろやかでうまみがあるとの評価を得ています。 |
||
| ◆いしいのそばで使っている塩の紹介◆ | ||
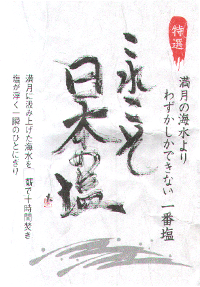 満月のj海水よりわずかしかできない一番塩 満月に汲み上げた海水を薪で十時間焚き、 塩が浮く一瞬のひとにぎり。 バランスの取れたミネラルを多く含んだ塩 |
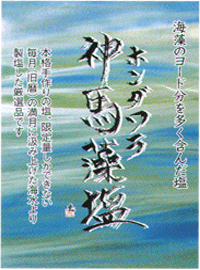 神馬藻(ホンダワラ)海藻に海水を かけ、乾かし、塩分を多く含ませ、 その神馬藻(ホンダワラ)海藻を焼い て水に溶かし、その上澄みを満月の 海水で煮詰めてて作られた。神馬藻 (ホンダワラ)海藻のヨード分を多く 含んだお塩です。 |
|
| 「特選、これこそ日本の塩」 ¥3675 「神馬藻(ホンダワラ)塩」 ¥3150 連絡先は下記の通りです。 製造者 : 小林 久 販売元 三好良社 住所 埼玉県草加市花栗4−2−20 TEL (048)943-1838 FAX (048)943-7863 |
||
| いしいのそば「塩そば」 | ||
| 福島本店では打ちたてのそばを湧き水 でたべる「水そば」 越谷分店ではそばを塩で食べる「しおそば」 とくに藻塩はまろやかでうまみがあり、めん つゆでは味わえないそばの味が楽しめます。 |
 |
|
| 塩そばの歴史 | ||
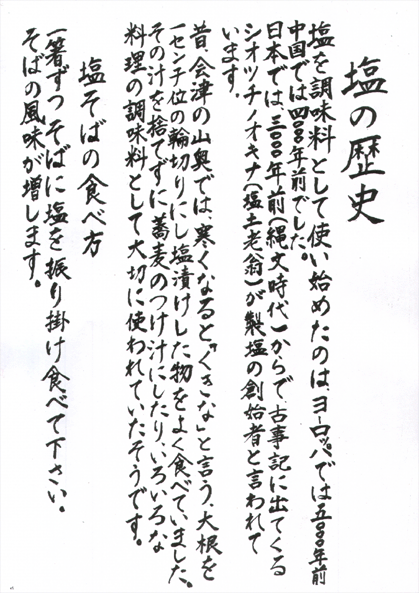 |
||
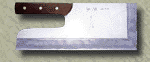 戻る |
|||
| いしいのそばトップページへ | 水そばの里 福島本店の紹介へ | 塩そばの越谷分店の紹介 | |